日本の貴重資料、どんな風に保存されてきたの?歴史を振り返る。
日本には数多くのすばらしい文化財があります。有形文化財と言われるものには、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などがあります。これらの貴重な文化財は、先人たちの努力によって現在に伝わっているものばかりです。
今回は、日本の貴重資料(主に建造物以外の文化財)が、これまでどのように保存されてきたのか、現代にいたるまでの資料保存の歴史を振り返りたいと思います。
目次
近代以前の資料保存方法
いまでこそ、貴重資料(文化財)の保存といえば、様々な科学的知識や技術が用いられていますが、当然ながらかつてはそのような技術も機器もありませんでした。それでもはるか昔から貴重資料は非常に効率的な方法で保存されてきたのです。
日本の風土に適応する保存方法の模索

まず、そもそもの話になりますが、日本は春夏秋冬という四季の変化に富んだ気候風土が特徴です。そうした季節の移り変わりにともない、花鳥風月を愛する繊細な美意識が育まれ、日本独自の文化や風習が培われてきました。
ただし、一年の間で気候の変動が大きいということは、資料の保存という観点からすると決して好ましくはありません。夏場の高温多湿の環境は、カビや虫の発生の要因となりますし、冬場の乾燥は木や漆の亀裂といった損傷を誘発します。こうした年間の温湿度の変動に加えて、日本は台風や津波、そして地震といった天災も諸外国に比べて多く、そうした災害によって失われた貴重な資料も少なくありません。
このような(資料にとっては)厳しい自然環境の中で、何百年も前の貴重な資料を現代のわたしたちが目にすることができるのは、過去の人々が資料を後世に残そうとする努力を惜しまなかったためです。
資料が劣化したり損傷したりする主な原因としては、経年劣化(温度、湿度、空気、光の影響)、虫害、火災、自然災害などがありますが、日本人はこの国の気候に応じ、そして資料のそれぞれの材質の特性を踏まえて、対処方法を編み出してきたのです。
それでは過去行われてきた保存の具体例を見ていきましょう。
保存の基礎がつまった正倉院宝物

毎年、秋の奈良をにぎわせるのが、上写真の奈良国立博物館で行われる「正倉院展」です。普段は非公開の正倉院宝物を一目見ようと、大勢の人が博物館に訪れる光景はもはや奈良の風物詩となっています。
正倉院は、もともと東大寺の宝庫だったものです。756(天平勝宝8)年に光明皇后が、聖武天皇遺愛の宝物などを東大寺に奉納しました。これが正倉院宝物の成り立ちです。
正倉院宝物には、東大寺の法会に用いられた仏具や、シルクロードを通じて伝わった中国、西域、ペルシャの文物など貴重な品々が含まれています。そして1000年をはるかにこえる時を経ても、これらの正倉院宝物は良好な状態で伝わっているのです。この正倉院宝物には、日本の資料保存の基本的な考え方がすべてつまっていると言っても過言ではありません。
正倉院宝物の良好な保存状態の秘密を探ると、まず一つに檜造りで高床形式という正倉院の建築構造があります。調湿能力の高い木質の空間内では、一日の中で変化する湿度の幅が、外気の1/5になることが分かっています。そして建材の檜が発するヒノキチオールは防虫効果があるため、害虫を寄せ付けません。
この優れた建造物の中で、各宝物はさらに唐櫃という木製箱に収納されています。これにより、湿度の変化が外気変化量の1/50にまで減少するという効果が認められています。気温に関しても同様に外気の影響をほとんど受けなくなり、良好な保存環境が保たれることになります。また唐櫃に入れることで、ネズミなどに食い荒らされる危険も格段に減るのです。
そして、正倉院で今も毎年行われている曝涼も、保存のために生まれた先人の知恵です。曝涼は、気温が涼しく湿度も低い秋に、点検を兼ねて宝物を箱から出し、箱の中にたまった湿気を逃がす作業です。蔵の中にしまわれ、さらに箱に収められた状態は、箱内に必要以上に湿度を残留させる恐れがあるため、特に紙や布素材の保存のためには曝涼は必要不可欠なものです。
そして正倉院が勅封という厳重な管理体制で守られてきたことも、保存の観点からすると大きな意味をもっていました。勅封とは、天皇による施錠という意味で、正倉院の扉は代々天皇の許しがなければ宝庫の解錠ができないよう固く閉ざされていたのです。
宝庫への出入りは曝涼の時に限定され、それによって庫内の温湿度の変動は最小限に抑えられ、日光の紫外線などのダメージも回避することでできました。
- 温湿度の変化を抑える。
- 湿気がたまることを防ぐ。
- 資料の使用回数を制限する。
こうした今でも資料保存の基本として実践されていることが、すでに奈良の時代から行われていたのですから驚きですよね。
蔵による保存

奈良時代から続く資料保存の好例として正倉院をご紹介しましたが、このように日本では資料を収める蔵が保存のための重要な役割を果してきました。資料保存の基本は、安定した環境で資料を保管することです。
日本で弥生時代の遺跡に、地上より高い位置に床面をもってくる高倉と呼ばれる構造の蔵が認められます。すでに湿気や鼠などの対策をとっていたことがわかります。
鎌倉時代には、火災対策として厚い外壁で構成された土蔵が登場し始めます。泥土を何層も塗り重ね、表面に漆喰を塗った外壁と、木の柱で作られた土蔵は、防火性能だけでなく、大気中の余分な湿度を吸収し、庫内の湿度を一定に保つ機能があります。さらに白い漆喰には太陽光を遮断する効果もあります。こうした高機能な土蔵を、寺院や神社は大事な寺宝・社宝などを収める宝庫として使用してきました。
桐材の使用

蔵の中に収められる時に、は資料はむき出しの姿ではなく一つ一つ箱に収納されました。
この収納箱に主に用いられたのが桐材です。桐は木材の中で最も吸湿の少ない特性を持ちます。そして空気を多く含む材質であるため、箱の内と外に空気層を作る効果があります。こうした特性から桐箱の中は温湿度の変化が非常に少なく、外気が変動しても安定した環境を作ることが可能です。
また桐は非常に燃えにくい材質です。空気を多く含む桐は発火温度が270度と大変高く、蔵が焼けても最後まで燃えずに資料を守ってくれるのです。
さらに桐は防虫成分のあるパウロニンやセサミンを含むため、桐箱は虫害が少ないというメリットがあります。さらに防腐効果の高いタンニンも含んでいるため、腐りにくく100年以上の長期間の使用に耐えるのです。
このように保存という観点からすると非常に有能な桐材を、数ある木材の中から見つけ、保存箱として使用することにした先人の知恵が、貴重な資料を守ってきたのだと言えます。
曝涼・虫干し

正倉院のところでお話しした曝涼ですが、日本では奈良時代から行われていたことが分かっています。寺の僧侶たちが経典などを風に通した後に保存するという営みを行っていたのです。
定期的な曝涼は、風にさらして湿気を逃がすという効果の他に、資料の点検を行い、状態の変化、問題の早期発見が可能になるという利点もありました。曝涼の時にカビや害虫を発見すれば、被害を最小限にとどめることができたのです。曝涼が虫干しとも呼ばれるのはこのためです。
江戸時代になると、梅雨明けの日差しの強い時に資料を日光にさらすということも行われました。これは直射日光に当てることで、日光消毒するという意味合いがありました。ただし紫外線の影響もあるため、短時間集中して行うことが推奨されていました。
中世、近世と寺社仏閣では年中行事として決まった時期に曝涼が行われ、この時に広げられた宝物は人々に拝観が許可されることもありました。いずれにしても、どんなに土蔵や桐箱の性能が良くても、資料をしまったまま放置してしまうことは避けなければいけません。それは現代の温湿度環境をコントロールできる収蔵庫でも、同じ事が言えるでしょう。
煙の活用

資料の保存には煙も活用されてきました。
例えば、奈良や鎌倉時代の仏像が虫に喰われることなく、今もその姿をとどめているのは、日々手向けられてきた線香のおかげです。杉の葉を膠で固めた線香は、虫が嫌う煙を出すため、線香で常に燻されている仏像は虫害から逃れることができたのです。
また、「おけら焚き」という風習があります。オケラとはキク科の多年草ですが、正月や節分の日に社前で篝火にオケラの根を焚いて邪気を祓いました。この「おけら焚き」は無病息災を願う風習でしたが、オケラの煙には、防湿・防虫・防黴の効果が認められることから、古くから梅雨時になると、蔵や納戸の中、また書庫などでオケラを焚くことが行われていました。
このように薬草の煙を昔の人は資料の保存に利用していたのです。
防虫効果のある植物の利用

いま紹介したオケラもその一つですが、先人たちは防虫効果のある植物や樹木に対する豊富な知識を持ち、資料の保存に用いてきました。
例えば、ショウガ科の多年草であるウコンで染めた黄色い布は、防虫効果が高く、古くから掛軸や巻子の包み布として使用されてきました。
また、乾燥させたクチナシの実は、文化財害虫であるフルホンシバンムシや紙魚(シミ)を防ぐ効果があるとして、絵画や書跡を収める桐箱には一緒にクチナシの実を入れる慣習がありました。他にも天然由来の防虫剤として、クスノキを原材料とする樟脳や、曼珠沙華の球根、銀杏の葉などが用いられました。
タデ科のタデアイによる藍染めは紙魚を寄せつけないとして、和装本の表紙などに好んで藍染めの紙が用いられていました。虫害の多い紙は、藍やクチナシで染める他、キハダの煮汁で染められることもありました。ミカン科のキハダは、強い抗菌作用を持つ染料として用いられ、キハダで染められた麻紙は黄麻紙、キハダで染められた楮紙は黄穀紙と呼ばれ、写経の紙などに多く用いられたのです。
近代以降の資料保存方法
資料の保存環境や保存方法についての先人たちの工夫や知恵をご紹介しましたが、近現代では科学技術を資料の保存に応用する試みがなされました。その具体的な取り組みを見ていきましょう。
燻蒸による殺虫・殺菌
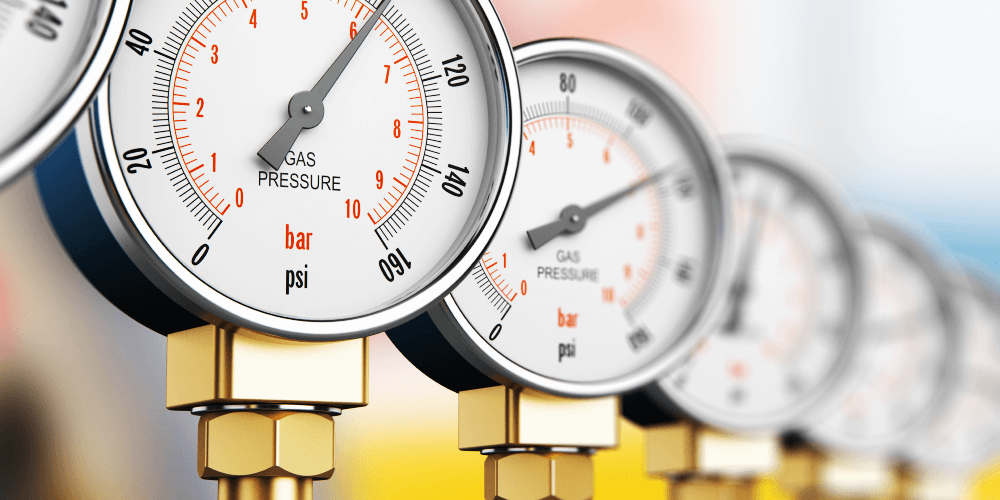
1940年代に、ガスを用いた密閉燻蒸が日本で行われるようになりました。最初に用いられたのは四塩化炭素でしたが、他にもガス燻蒸導入初期にはクロルピクリン、二酸化炭素などが燻蒸薬剤として用いられました。しかしいずれの薬剤も殺虫力が不十分であったり、金属や顔料を変色・変質させる懸念があったりと、何らかの問題を抱えていました。
その後に登場したのが、臭化メチルと酸化エチレンを混合した燻蒸用ガス・エキボンです。1960年代に開発されたエキボンは、1980年には文化財虫害研究所の文化財虫菌害防除薬剤として認定されました。エキボンは強い殺虫力、殺カビ力を持ちながら、大半の材質に対し変色などの影響を及ぼすことがないという利点があり、また浸透力、拡散力が強いことから複雑な構造の資料であっても細部まで殺虫、殺カビ効果がいきわたるということもあって、多くの美術館・博物館で使用されるようになったのです。
しかし、エキボンの主成分である臭化メチルがオゾン層を破壊する恐れがあるとして、1997年にモントリオール議定書会議を経て世界的に使用が規制されることになりました。日本では2005年には臭化メチルは全廃となり、燻蒸にエキボンを用いることが不可能になったのです。
これによって、資料を虫やカビから守るための手段は大きな方向転換を余儀なくされました。
IPM(総合的有害生物管理)

エキボンの全廃によって、薬剤に頼った燻蒸という方法が見直されました。
燻蒸に代わり、IPMという方法が提唱されるようになったのです。IPMとはIntegrated Pest Managementの略で、日本語に訳すと総合的有害生物管理といいます。虫やカビによる被害が起きてしまう前に、より積極的に予防しようという考え方が根本にあります。
このIPMは、もともと農業分野で研究、検討されてきた害虫防除の概念であり、
あらゆる適切な技術を相互に矛盾しない形で取り入れ、経済的な被害が生じない範囲内で害虫個体数を減少させ、かつその個体レベルを維持する害虫管理システム
と定義されています。要するに、害虫やカビを被害のない数にまで減少させ、その状態を維持しようとするものです。これが美術館・博物館の資料保存の分野でも応用されるようになったのです。
IPMは、害虫対策を燻蒸などの一つの方法に頼るのではなく、人体や資料に影響の少ない方法を複合的に用いる点が大きな特徴です。その方法を挙げてみると、
- 施設の内外で害虫の個体数やカビの発生の有無を調査する。
- 調査結果に基づき、虫の侵入経路をふさぐなどの対処をする。
- 収蔵庫の温湿度の測定記録を行う。
- 収蔵庫の掃除をこまめに行う。
- 対策の効果を定期的に確認し、改善する。
- 必要に応じて、計画的に最低限の燻蒸を行う。
ご覧いただくとわかるように、IPMは非常に地道な作業です。一つ一つの方法は単独で大きな効果を期待できるものではありませんが、こうした対策を日常的に行い、さらに毎年根気よく繰り返すことで効果を発揮するのです。
光学的な分析

資料の効果的な保存方法を考えるためには、その資料の材質や技法に関する情報を手に入れる必要があります。そこで活躍するのが光学的分析です。
光学的分析とは、電磁波(光)を用いた分析のことですが、電磁波は波長の長い順に、電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、γ線と分類されます。可視光線だけでも様々な情報を得ることができますが、それ以外の領域の波長を用いるとさらに多くの情報を得ることができます。
例えば、赤外線を使うと可視光線下では不鮮明だった墨書がはっきりと浮き上がってくることがあります。これは墨が赤外線を吸収しやすい材料であることを利用したものです。また紫外線を絵画作品に照射して、その蛍光現象の有無を確認することで、使われている顔料を推定したり、過去に修理された箇所を特定したり、といった使い方もあります。
強い透過力を持つX線は、資料の内部を撮影するために用いられています。X線を用いた分析方法としては、他に元素を特定できる蛍光X線分析や結晶質化合物の同定をするX線回析などがあります。
こうした分析方法を駆使して、資料一つ一つに必要な保存処置を検討するのです。光学的分析の多くは、非破壊・非接触で資料の情報を得ることができるため、貴重資料を扱う上で非常に有効な手段と言えるでしょう。
デジタルデータによる保存

近年最も技術が進歩し、さらに今後もさらなる活用が期待されているのが、デジタルデータによる資料保存です。
カメラやスキャナといった撮影機材の進化によって、貴重資料を非常に高精細なデジタル画像で記録することが可能になりました。当然データ容量も小さくはありませんが、撮影機材とともにパソコン処理速度の高速化、記録メディアの大容量化、低価格化が進んでいる他、データを管理するためのクラウドサービスの普及など、大容量データを扱う環境も着々と整ってきています。
資料そのものの保存とは若干意味が異なりますが、デジタルデータで保存することは資料にとっても有益です。
デジタルデータのメリットは数多くあります。
- 繰り返し使用しても劣化しない。
- 複製などの二次利用が簡単に行える。
- 不特定多数による共有が可能。
- データが増えても、収納スペースを増やす必要がない。
- 原物資料の使用を減らすことができる。
最後に挙げた、原物資料の使用を減らすことが、資料の保存にとって大きなメリットと言えるでしょう。この記事の最初に紹介した正倉院宝物の事例で分かるように、資料の使用回数をおさえることが資料を損傷から守るために重要であると言えるからです。
かつては、そのためには資料の非公開という手段をとるしかありませんでしたが、デジタルデータを活用することによって、貴重資料の保存と公開という相反するテーマを同時に達成することができようになったのです。
貴重資料の画像データを集めてデジタルアーカイブを構築し、インターネット上で全世界に公開する美術館、博物館が増えているのもこのようなメリットがあるからですね。
そのままスキャンでも、重要文化財をはじめとした様々な貴重資料を電子化してきました。非破壊スキャナーを使うことで、劣化の激しい資料でも傷めずそのままデータにし、データ上でも高度な画像修正技術で新品同様の色味を再現することに成功しています。実際に、弊社では日本を代表するお寺様・浅草寺様の蔵書300冊以上を電子化・テキスト化させていただき、資料内の情報を現代で活用できるようにさせていただきました(詳しくはこちらで紹介しています)。
資料原本はそのまま保管し、その中身・情報=データを使っていくという流れが顕在化していると言えるでしょう。
大切に保存されてきた貴重資料をさらに未来へ

科学的な保存技術が発達するはるか昔から、人々が貴重な資料を保存するために行ってきた歴史を駆け足でご紹介しました。
先人たちの工夫を見ると、その合理性に驚かされます。そして同時に、どんなに科学技術が発達しても、資料を守るためには、扱う人間が資料をよく観察してその素材の特性や弱点を知り、それぞれに適した処置を検討する必要があることを教えられます。
過去の人々の努力で今に伝えられてきた貴重な資料を、わたしたちもまた次の世代、そしてさらに未来へと受け継いでいく使命があります。そのために、伝統的な保存方法と最新の科学技術の両方を柔軟に織り交ぜて、資料を守っていかなければいけませんね。
